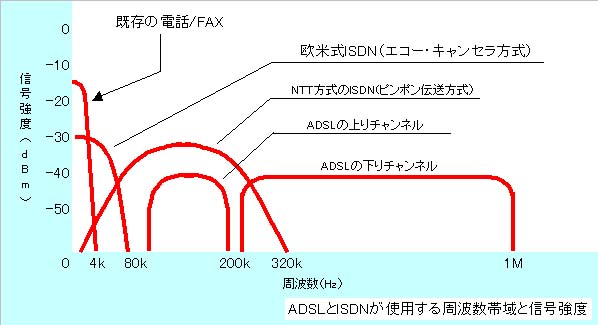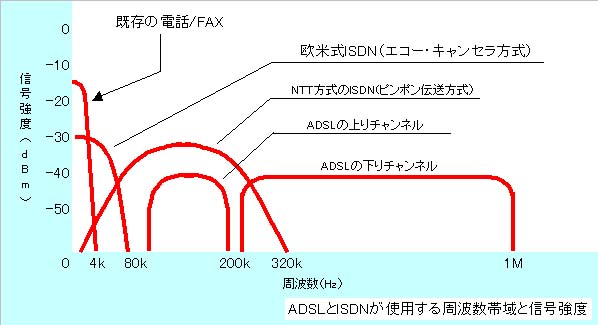xDSLの問題点の一つに、伝送距離があげられる。xDSLでは周波数の高い信号線を伝送するため、ノイズに弱く、伝送距離による信号の減衰も大きい(図参照)。一般に、ADSL技術を使って1.5Mビット/秒の伝送速度(下り方向)を確保できるのは最長5.5km程度といわれている。この結果、米国ではADSLの利用を想定した場合、利用可能なユーザは8割弱となる。NTTがADSLを前向きに検討してこなかった理由の一つでもある。ただ、米国では他にもケーブルモデムや衛星といった選択肢があるため、使えないユーザがいても仕方がないと割り切ってしまっている。
また、モデム同士の相互接続性にも問題がある。同一メーカの製品同士でしか通信できないのが現状である。信号の変復調方式,CAP(*1),DMT(*2)の2種類があり、どちらが今後の主流になるかは、まだわからない。
|